2025年5月15日X投稿より
アオミオカタニシ(学名:Leptopoma nitidum)は一部の奄美群島を除く琉球諸島、台湾 、パプアニューギニア、インドネシアなどで生息が確認されている陸生巻貝です。
詳しい食性が解明されておらず中華圏では青山蝸牛は蘚苔類(苔)や地衣類(菌類と藻類の共生体)を食べると言われ、日本ではすす病(糸状菌)に罹患した葉を供することで長期飼育が実証されています。
エメラルドグリーンに近い綺麗な殻と触角の根元に位置する愛くるしい黒い目が特徴で観賞価値が非常に高く、流通価格も安価であることからもっと人気がでてもおかしくないと考えますが、具体的な餌が不明であり判明している餌も持続的な調達が困難であること、そして環境省レッドリストの準絶滅危惧に掲載されていることが普及への障壁となっていると考えられます。
一方で近年の生物飼育の多様化より様々な生物が捕獲され飼育されるようになりましたが飼育方法が確立されていない種の採取やエゴ的な看取り飼育は芳しいとは言えず、況して希少種ともなれば目先の利益を優先したり飼育記録を競うのではなく飼育インフラを構築するための研究を優先すべきであると考えます。
流通単価は安いものの準絶滅危惧ということもありアオミオカタニシの効率的な飼育方法を攻略しようと考えましたが、実のところ興味を持ったのは特殊な食性があるのではないかと考えたためです。
アオミオカタニシは人間の生活圏で発見されることがあるにもかかわらず何を食べているのかわからないということは、餌を食べていることに気付かないのか餌を食べないということが考えられます。
前者については軟体動物の多くはヤスリ状の歯舌を持ち、時に移動しながら餌を削り摂餌します。
すす病に罹患した葉は表面に黒いすすが付着することで確認され、すすが綺麗に無くなればアオミオカタニシが削って食べたという情報が視覚で確認できます。
自然界には視覚で確認しにくいものも多く存在し自然下では陸生のカタツムリやナメクジのように葉や樹皮に発生したカビなどの菌類を食べていると想像できます。
現状ではアオミオカタニシは野生個体が採取され飼育されることになりますが、隠れ家や足場として生息地の葉や枝なども採取され飼育下に持ち込まれることがあります。
また、糞便から消化されなかった菌類などの胞子が排泄されることでアオミオカタニシの餌として用意された昆虫ゼリーや床材として用意されたキッチンペーパーなどを培地として増殖します。
生息地から持ち込まれたこれらの菌類などを食べることでしばらく生き存えることができます。
尚、生物飼育には香料、保湿剤、蛍光染料配合の可能性があるティッシュペーパーなどは使用せず、食品に使用できる基準を満たしたパルプ100%のキッチンペーパーを使用することをお勧めします。
台湾の愛好家の間では定期的に自然界から葉や枝を採取し水で濡らした後飼育ケースに入れる飼育方法があるようです。
これらの菌類は例えば生菌としての麹菌や酵母菌の胞子や胞子を激活(菌起こし)したもので手軽に代用できると考えられます。1)
カビは菌糸を成長させるとき環境中のカルシウムイオンを取り込むことがわかっていますので水溶性カルシウムを併用するとカビの成長が速く、同じくカルシウムを必要とするアオミオカタニシにも有効であると思われます。
次に後者ですが、アオミオカタニシの分布から考えると太古の海退により海洋性巻貝が陸に残され一旦淡水化したかどうかは定かではありませんが、後に地殻変動で移動したのではないかと思われます。
生物のなかでも腹足類(巻貝)は積極的に陸上生活に適応した動物であると言われています。
水生のタニシは藻類を好んで食べますが陸上で得られる藻類の量は圧倒的に少なくなるのではないでしょうか。
例えば水生藻類は大量生産が可能なバイオマス原料として培養が盛んに行われますが陸生藻類を培養することはありません。
環境変化により餌がなくなると生物は餓死するか別の餌を探すことになりますが、湿度が高い地帯で岩や植物に局地的に発生する水生藻類に近い藻類(風で飛ばされた水生藻類の胞子かもしれませんが)の他はやや乾燥地帯に生息する気生藻や地衣類に依ることになります。
しかし気生藻や地衣類をアオミオカタニシが好んで食べることはなく、苔にしても本体を食べる様子は伺えずせいぜい胞子や不定芽を食べる程度ではないかと思われます。
既述のようにアオミオカタニシは緑色の殻を持ちますが実際の殻は薄い乳白色で外套膜が透過して見えている状態にあります。
沖縄諸島には形状が似たオキナワヤマタニシ(学名: Cyclophorus turgidus turgidus)が生息していますが殻の性質はやや異なるようです。
このことは非常に興味深い特徴でありアオミオカタニシの食性と大きな関係があるのではないかと考えました。
貝類の殻は外套膜から分泌される炭酸カルシウムの結晶で形成されるため無色から白色をしていますが環境や食物の影響で色素が混ざり多用に変化します。
貴重な藻類を有効利用するために同じ腹足類である一部のウミウシに見られるような餌として食べた藻類から色素体(葉緑体)を細胞内に残す盗葉緑体現象(Kleptoplasty)がアオミオカタニシにも見られるのではないかと考えました。
夜間に活動し藻類などから葉緑体を細胞内に集めて昼間は木の幹や葉に留まり、安全なサンルームにこもりながら日光浴を行うことで栄養を生産することは餌の少ない陸上での効率的な生き残り戦術であったのかもしれません。
また、葉緑体を保存できる期間によっては陸上で長期のクリプトビオシス(乾眠)に近い状態を維持することも可能であったかもしれません。
アオミオカタニシの好物には大量培養可能な緑藻も含まれ特に水槽壁面に付く遊走子(zoospore)であると言えます。
このように人工的に生産できるアオミオカタニシの餌を例として共有させていただきました。
緑藻の遊走子に関しては水槽などの容器で培養する際にある程度の液肥を必要とし副産物として緑水が生産されることやその緑水を種水として保存する必要が課題と考えられます。
現在、保存性と再現性に優れた緑藻や苔の胞子をインスタント飼料として使用する実験段階に入りましたので成果が現れましたら報告させていただきます。
参考
1)枯葉を用いた麹菌培養
使用する葉や枝などの原料は薬剤使用の無いものを用意します。
枯葉は保存性が優れていますので当店では枯葉を使用します。
枯葉を5%糖液の入った容器に浸し電子レンジで1分程度殺菌処理します。
糖液には更に食品添加物としての塩化カルシウムを混ぜておきます。
加熱が終了したら原料を糖液から取り出し冷めるまで待ちます。
冷めた後、種麹の接種を行い雑菌の混入防止と十分な湿度を保てるように食品保存用袋に入れ35℃を保ちます。
通常の麹菌の発酵には2日ほどかけますが概ね1日待てば良いかと思います。
麹菌は好気性菌なので数回は酸素を供給してください。

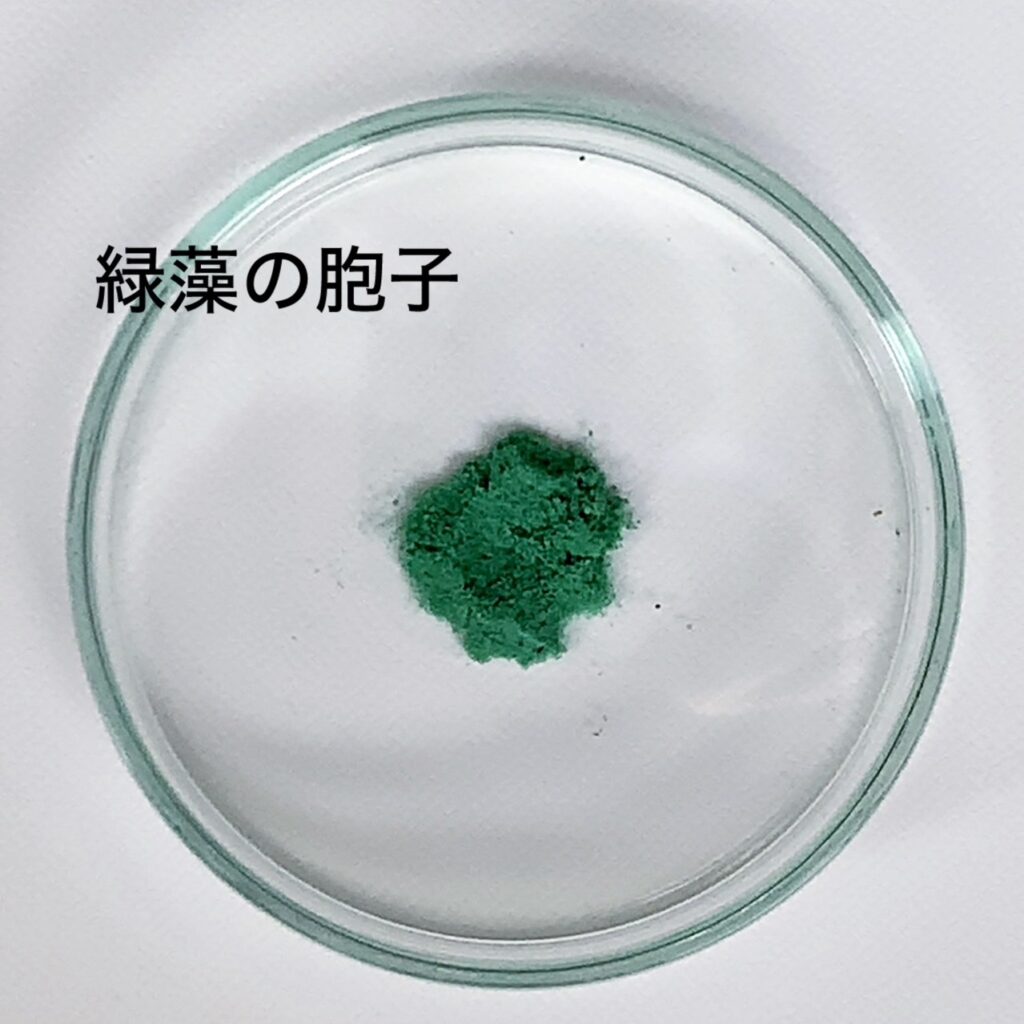
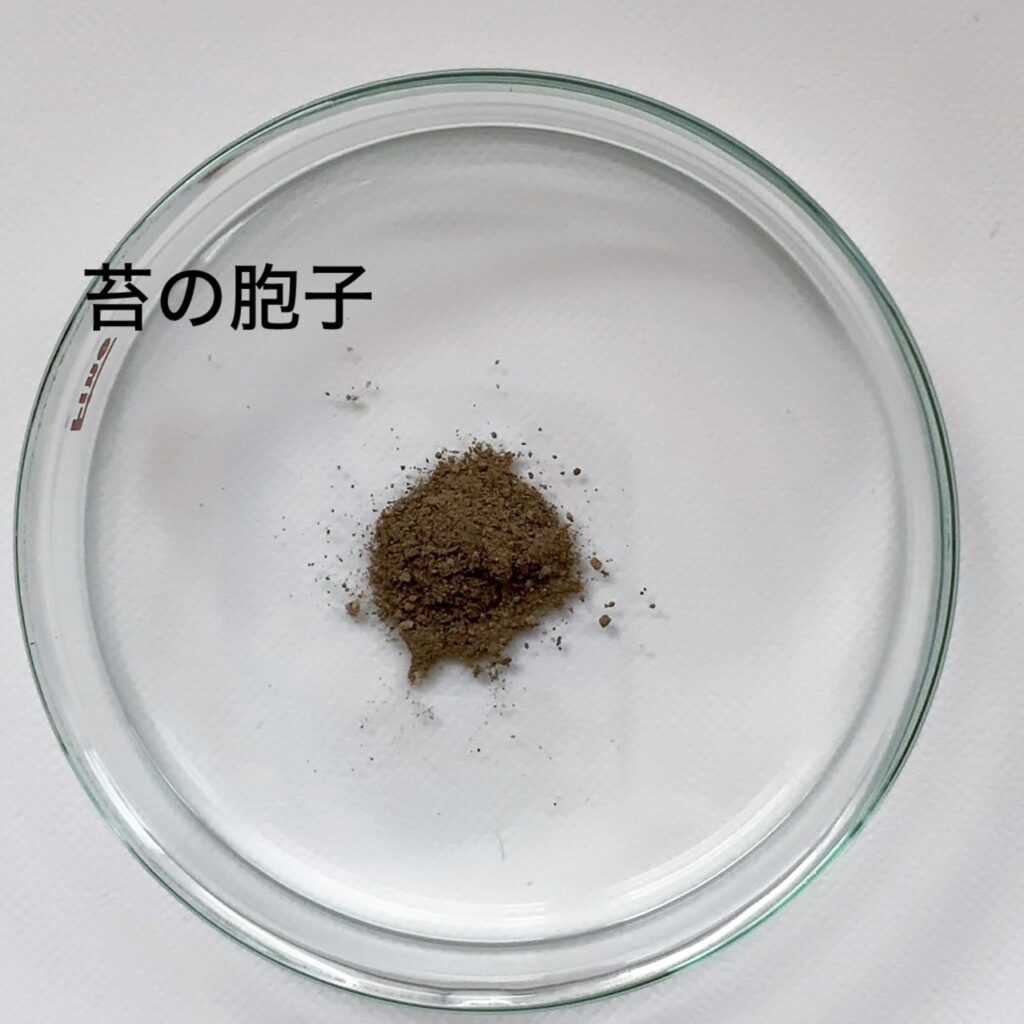
著者について